
生前における遺留分対策の可否とその方法
事例で考える相続
2023/08/22
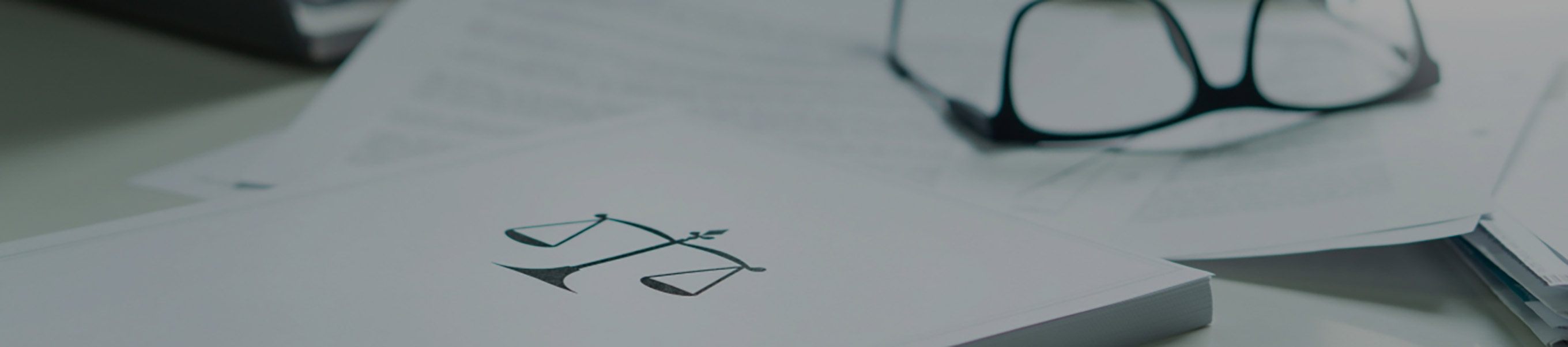

私は、会社を定年退職した後、退職金を元手に株や投資信託等で運用し、退職金を2倍ほどに増やすことができました。妻とは死別していますので、私の財産は、3人の子供たちに相続させたいと思っていますが、子供たちには私の財産を巡ってもめてほしくないので、もめることがないように、遺言を残したいと思っています。

そこで、子供たちがもめないように、この株は長男、この投資信託は次男、マンションは三男など、財産ごとに細かく分割方法を指定して遺言書を作成しようと思ったのですが、投資信託や株式ついては、商品名や会社名だけで足りるのか、その他に遺産を特定するために何を書かなければいけないのかがよく分かりません。
遺言書は全部手書きしないと無効だとインターネット上に書いてましたが、そもそも金融商品等は商品名等も複雑なことが多く、それらをすべて手書きするのはとても大変です。
子供たちのために遺言書を作成しておいた方がいいということはわかるのですが、もっと手軽に遺言書を作れないものでしょうか?
※架空の事例です。
相続法の改正により、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、その目録は自書が不要となり、また、通帳や登記事項証明書のコピーも目録として添付できるようになりました。
詳細については以下で見ていきましょう。
相続法改正前は、自筆証書遺言については、財産の目録も含めその記載内容のすべてを自書しなければいけないとされていました。
一般論として遺言書を作成する方は高齢であることが多く、高齢者にとって遺言書のすべてを自書することはとても負担ですので、例えば誰かに代わりに書いてもらったり、パソコンで印字したものを利用したいという思いは理解できなくもありません。
特に、遺言で特定の財産を特定の相続人に相続させるとの内容で遺言書を作成する場合、財産の特定のために必要十分な記載をするなど、作成の負担はより重いものとなります。
しかし、本人の「自書」ではない遺言書について、相続法改正前は、遺言の方式要件を満たさず無効とされていました。
このように、相続法改正前における自筆証書遺言は、高齢者にとって一見すると手軽なようであり、実は作成のハードルが高い形式の遺言であったといえます。
そこで、改正相続法では、自筆証書遺言をより作成しやすいものとするために、自筆証書遺言に目録を添付する場合、その目録については自書が不要と改正されました。
これにより、財産の特定のために細かい記載を自書する必要もなくなり、書き間違い等により相続手続を進められないという事態も回避できるようになりました。
もっとも、目録の偽造や変造のリスクはあるため、偽造等を防止する趣旨で、自書ではない目録の場合には、目録の各ページに遺言者の署名押印をしなければならないとされています。
なお、施行日は、改正相続法の中で最も早く、2019年1月13日から施行されています。
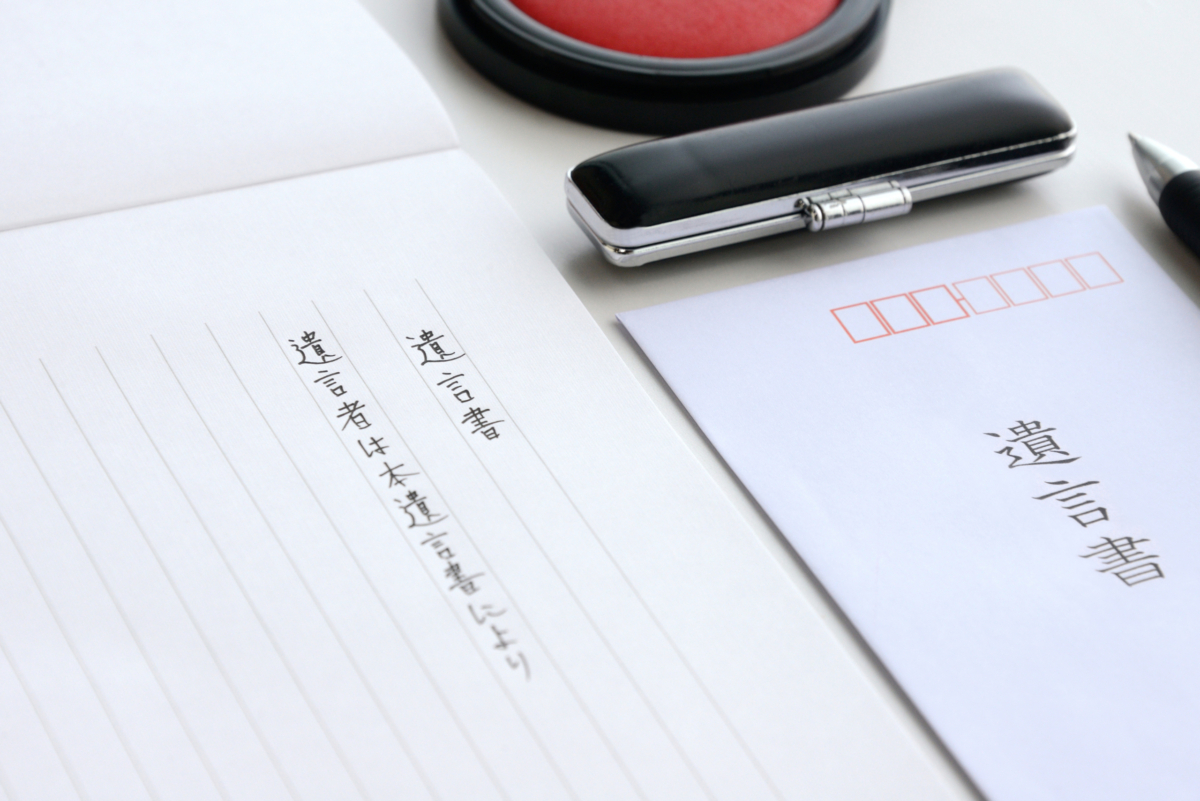
財産目録については、各ページに遺言者の署名押印が要求される以外、特段の制限はありません。
そのため、Excelなどで財産目録を作成することも可能ですし、不動産の登記事項証明書や預金通帳、残高証明書、証券会社からの取引報告書などの書面のコピーを目録として添付することもできます。
なお、相続法改正の内容は、自筆証書遺言に目録を「添付する」場合に自書性を緩和するというものですが、「添付」とは、本文とは別の用紙を付け加えるという意味ですので、自書によらないことが許される目録は、本文とは別の用紙で作成される必要があります。
そのため、例えば、A4の紙の上部に自書で遺言の本文を、用紙の下部にパソコンで印字された目録が記載されている場合、その遺言書は無効とされてしまいます。
本文を記載する用紙は依然としてすべて自書により作成する必要がありますので、自筆証書遺言の作成の際はご注意ください。
POINT 01 相続法改正により自筆証書遺言の方式が緩和
POINT 02 遺言に添付する財産目録については自署は不要
POINT 03 依然として本文については自書が必要
いかがでしたか。相続法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和され、遺言に添付する目録については自書する必要がなくなりました。これにより、一般論としては自筆証書遺言が作成しやすくなったといえるでしょう。
事例のケースでは、証券会社から届いた取引報告書等のコピーを目録として添付することで、遺産が特定できないリスクもなくなりますし、自書する手間も省くことができますので、全文自書の場合と比べて、手軽に自筆証書遺言を作成することができるようになったといえるのではないでしょうか。
しかし、作成後にそのまま自宅の机等で保管した場合、依然として隠蔽や改ざん等のリスクがあります。そこで、自筆証書遺言を作成する場合には、併せて改正のあった、自筆証書遺言の保管制度の利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
遺産相続・税務訴訟
・その他の法律問題に関するご相談は
CST法律事務所にお任せください
03-6868-8250
受付時間9:00-18:00(土日祝日除く)
